2024年2月13日放送の【クローズアップ現代】で取り上げられた『ライドシェア』
放送を観て、「ライドシェアはどの地域で利用できるの?」「ライドシェアの利用方法は?」と思われた方もいるのではないでしょうか?
今回の記事では
- ライドシェアって何?
- ライドシェアが導入される地域
- ライドシェアの利用方法
について書いていきたいと思います☆
ライドシェアって何?

『ライドシェア』とは一般ドライバーによる自家用車の相乗りサービスです。
ライドシェアには・・・
この2つのタイプがあり、海外では両タイプのライドシェアが普及しています。
一方で、日本では第2種免許を持たない人が有償で送迎することは、いわゆる「白タク」行為に当たるとして、厳しく規制されてきました。
しかし、岸田総理は2024年4月から地域や時間帯を限定して一般ドライバーが有償で送迎する「ライドシェア」の運用を開始すると発表しました。
まずはタクシー会社管理のもと行われ、「全面解禁」については2024年6月に方針のとりまとめを目指しています。

利用者にとっては、タクシーを使いたい時によりお得に移動できるようになれば嬉しいですね♪
ライドシェアが導入される地域
現時点では明確に導入地域は決まってはいないようです。
ただ、全国の108の自治体の首長が「自治体ライドシェア研究会」に参加を表明しており、今後各地域でライドシェアの導入に向けて本格的な議論と検討が行われていきます。
タクシーが不足する過疎化地域や、都市部でも深夜帯などで導入が検討されています。

過疎化地域の高齢者が携帯アプリを使うハードルは高いので、誰でも利用できる仕組みができると嬉しいですね☆
ライドシェアの利用方法

現在のライドシェア利用方法は、携帯アプリの登録となっています。
現時点で、ライドシェアの主なアプリとしては・・・
- notteco
- mobi
- 相乗りタクシー「AINORY]
- 相乗りタクシー「nearMe.」
などがありますが、「タクシー会社管理のもと・・・」ライドシェアがスタートするのであれば、『Uber』や『DiDi』、『GO』などの既存の配車アプリが活用される可能性が高そうですね。

アプリだと、過疎化地域の利用に課題が残りそうです・・・
まとめ
- 2種免許を持っていない人が有償で運転するライドシェアが、日本でも2024年4月からタクシー会社管理のもと導入される。
- 導入される地域は明確になっていないが、全国108の自治体が検討を進めている。
- 現時点での利用方法は、携帯のアプリが想定される。
時代を考えると仕方のないことかもしれませんが、デジタルの普及が進む中で、過疎地域の利便性の向上を考えることは今後も課題となりそうですね。。。
最後までお読みいただきありがとうございましたm(__)m
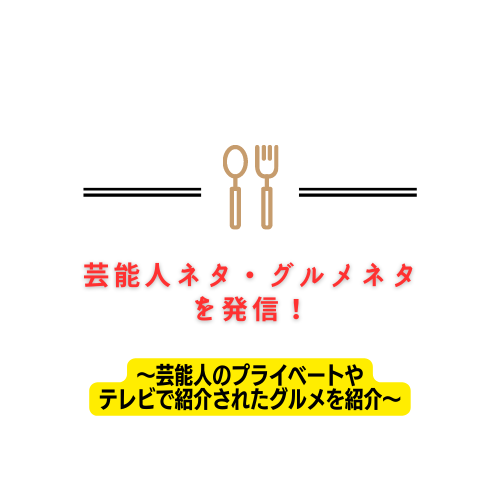



コメント