連続テレビ小説(通称:朝ドラ)『あんぱん』が2025年3月31日にスタートします。

朝ドラ『あんぱん』は、「アンパンマン」を生み出したやなせたかし(北村匠海)と暢(今田美桜)の夫婦をモデルに、生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかった二人の人生。
何者でもなかった二人があらゆる荒波を乗り越えて、「逆転しない正義」を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでを描き、生きる喜びが全身から湧いてくるような「愛と勇気の物語」が描かれます。
脚本は、「ドクターX」などを手掛けた中園ミホさんで、モデル人物はいるものの、物語自体はフィクションを加えたオリジナルストーリーであることも発表されています。
放送を観て、
「朝田のぶの実在モデルは誰?」
「実際の朝田のぶはどんな人だったの?」
なんて思われた方もいるのではないでしょうか?
今回の記事では・・・
- 朝田のぶのモデルとなった小松暢はどんな人だったのか。
- 小松暢(朝田のぶ)が生きた日本の時代背景
について紹介したいと思います。
この記事を読み、朝田のぶのモデル小松暢と、『あんぱん』の時代背景を知ることで、『あんぱん』をより深く楽しむことができますので、ぜひ最後まで読んでみてください☆
1.朝田のぶのモデルになった人物は誰?

今田美桜さんが演じている朝田のぶのモデルとなっているのは、やなせたかしさんの妻である小松暢(こまつのぶ)さんです。
1-1.小松暢(朝田のぶ)のプロフィール
・名前:小松 暢(こまつ のぶ)
・生まれ:1918年
・出身地:大阪府大阪市生まれ。父が『あんぱん』の舞台である高知県安芸市(あきし)の鈴木商店で勤務していた。
・性格:元気で明るく前向き。男勝りな性格。
・あだ名:「ハチキンおのぶ」「韋駄天おのぶ」
※ハチキン=土佐弁で、男勝りな性格の女性を表す言葉。韋駄天=足の速いことを表す言葉。由来は仏教の守護神。
・仕事歴:1946年に「高知新聞」が採用した女性記者2人のうちの1人。当時女性の新聞記者は非常に珍しかった。その後、代議士の秘書になるため東京に上京。
・やなせたかしにかけていた言葉:「なんとかなるわ。収入がなければ、私が働いて食べさせるから」
非常に前向きで元気な女性だったようですね☆
男勝りはおいといて・・・朝田のぶさんを演じる今田美桜さんや、その幼少期役を演じる永瀬ゆずなちゃんのイメージもぴったりではないでしょうか^^
2.小松暢(朝田のぶ)が生きた時代背景
ここからは、小松暢さんが生きた時代の日本がどのような状況だったのか、時代背景を見ていきたいと思います。
2-1.1918年(生まれた年)~1920年代(幼少期)

小松暢(こまつ・のぶ)の生まれた1918年(大正7年)から幼少期の時代(1920年代)は、日本にとって大正時代から昭和初期にかけての変革期。
1. 大正デモクラシーの時代(1910年代後半〜1920年代前半)
1918年は大正時代(1912~1926年)の中期にあたり、政治や社会が大きく変化していた時期。
- 第一次世界大戦(1914~1918年)が終結し、日本は戦勝国となった。
- 工業化が進み、都市部の発展が加速しました。特に東京・大阪などの都市では近代化が進んだ。
- 大正デモクラシーと呼ばれる自由主義・民主主義的な動きが活発になり、普通選挙を求める運動や労働運動が盛んになった。
2. 米騒動(1918年)
小松暢が生まれた1918年は「米騒動」の年でもある。
- 米の価格が急騰し、全国的に暴動が発生。
- 貧しい庶民が高騰する米を買えなくなり、特に漁村や農村の女性たちが中心となって暴動を起こした。
- これがきっかけで、内閣が交代し、原敬(はら たかし)が日本初の政党内閣を組織した。
3. 関東大震災(1923年)
小松暢が5歳の時(1923年)、関東大震災が発生。
- 東京・横浜を中心に大きな被害を受け、14万人以上が亡くなったとされている。
- 復興の過程で、東京の街並みが近代的に整備された。
4. 昭和時代の始まり(1926年~)
小松暢が8歳になる1926年に昭和時代(昭和元年)が始まった。
- 昭和恐慌(1927年):金融不安による大規模な経済危機が発生。
- 満州事変(1931年):中国での軍事行動が本格化し、日本は戦争へと進んでいく時代へ向かった。
2-2.1938年(20歳)~1958年(40歳)

小松暢(こまつのぶ)が成年(20歳)になる1938年(昭和13年)から40歳になる1958年(昭和33年)の期間は、戦争と戦後復興、高度経済成長の始まりという大きな時代の変化があった。
・日中戦争の激化(1937~1945年)
- 1937年に始まった日中戦争は、1938年には本格的な長期戦に突入していた。
- 日本は総力戦体制に入り、経済や産業が軍事優先となり、国民生活にも影響が出始めた。
・第二次世界大戦と太平洋戦争(1941~1945年)
- 1941年12月、日本はアメリカ・イギリスなどと開戦し、太平洋戦争が始まった。
- 戦争が進むにつれ、徴兵制の強化、食糧難、空襲などで国民生活は極端に厳しくなった。
- 1945年には、東京大空襲や広島・長崎の原爆投下などで日本は壊滅的な被害を受け、8月15日に終戦を迎えた。
・GHQ(連合国軍総司令部)による占領(1945年~1950年)
- 日本はアメリカを中心とするGHQの占領下に置かれた。
- 軍国主義の廃止、戦争責任の追及(東京裁判)、民主化政策(農地改革・財閥解体)が進められた。
・極度の食糧不足と闇市(1945年~1950年)
- 戦争によって国内の生産力が低下し、食糧難が深刻化。
- 配給制度は崩壊し、多くの人が闇市で生活必需品を入手するようになった。
・日本国憲法の制定(1947年)
- 1947年に新憲法が施行され、日本は「戦争放棄」「民主主義」「基本的人権の尊重」を掲げる国となった。
・朝鮮戦争(1950~1953年)と特需景気
- 1950年に朝鮮戦争が勃発し、日本はアメリカ軍の補給基地となり、大量の軍需物資を生産。
- これにより日本経済は急速に回復し、戦後の混乱から立ち直るきっかけとなった。
・サンフランシスコ講和条約(1951年)で独立回復
- 1952年、日本は独立を回復し、国際社会に復帰。
・高度経済成長の始まり(1955年~)
- 1955年頃から日本は高度経済成長時代に突入し、工業化が進んだ。
- 電化製品(テレビ・冷蔵庫・洗濯機)が普及し、都市部の生活が豊かになった。
- 1956年の「もはや戦後ではない」(経済白書)という言葉が象徴するように、日本経済は力強い成長を始めた。
2-3.1958年(40歳)~1973年(アンパンマン誕生)

小松暢(こまつ・のぶ)が40歳(1958年・昭和33年)から55歳(1973年・昭和48年)までの期間は、日本が本格的な高度経済成長を遂げ、国民の生活が大きく向上した時代。しかし、その一方で公害問題や社会の変化も進んだ時期でもあった。
① 高度経済成長のピーク(1958~1964年)
・三種の神器(白黒テレビ・冷蔵庫・洗濯機)の普及
- 1950年代後半から、日本の家庭では「三種の神器」と呼ばれた白黒テレビ・冷蔵庫・洗濯機が普及し、生活が一気に近代化した。
・東京オリンピック(1964年)とインフラ整備
- 1964年の東京オリンピックは、日本の戦後復興の象徴となった。
- 東海道新幹線や高速道路(名神高速など)が開通し、都市部と地方の移動が格段に便利になった。
② 国民の暮らしの向上(1965~1970年)
・GNP世界2位へ(1968年)
- 1968年、日本のGNP(国民総生産)はアメリカに次いで世界第2位となった。
- 自動車・家電・鉄鋼・造船などの産業が急成長した。
・「新・三種の神器」(カラーテレビ・クーラー・自動車)
- 1960年代後半には、カラーテレビ・クーラー・自動車が普及し、多くの家庭がより快適な生活を送るようになった。
・公害問題の深刻化
- 急激な工業化により、四大公害病(イタイイタイ病・水俣病・四日市ぜんそく・新潟水俣病)が社会問題になった。
- 1970年には「公害国会」が開かれ、環境規制が強化された。
今後、『あんぱん』で今田美桜さん演じる朝田のぶが、これらの時代背景とどのように関連しているのか見ていくと、朝田のぶが、いかに激動の時代を生きてきたかがわかるのではないでしょうか。
まとめ
- 今田美桜演じる朝田のぶのモデル人物は、やなせたかしの妻である小松暢
- 朝田のぶの幼少期から、アンパンマン誕生の1973年までの日本は、まさに激動の時代だった
小松暢さんは、「正義は逆転することがある。信じがたいことだが。じゃあ、逆転しない正義とは何か?飢えて死にそうな人がいれば、一切れのパンをあげることだ」という言葉でやなせたかしさんを励ましていたそうです。
最後まで読んでいただきありがとうございましたm(__)m
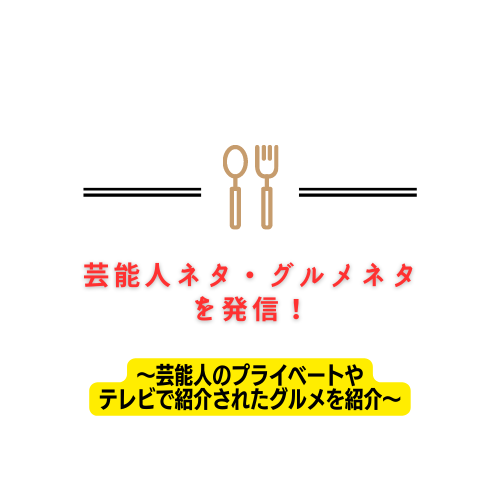
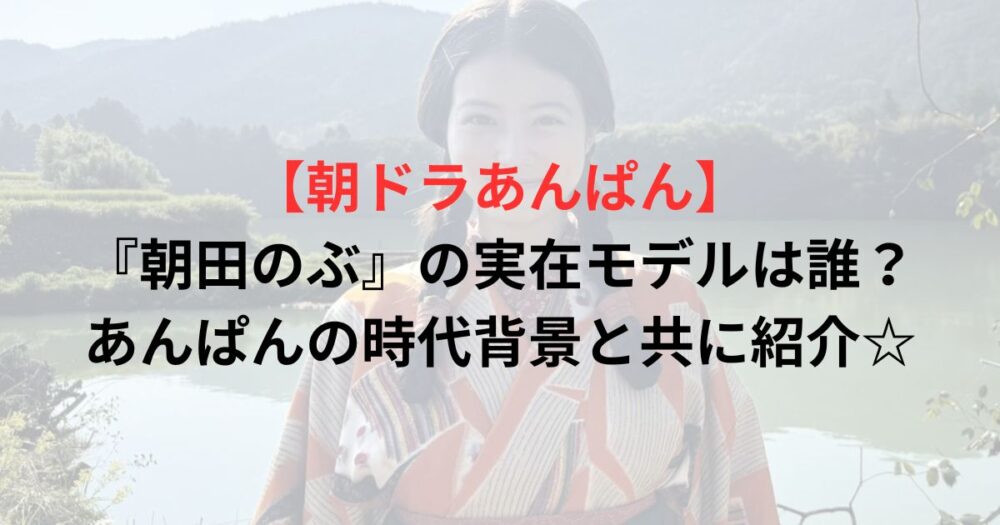


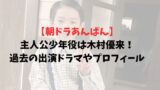
コメント